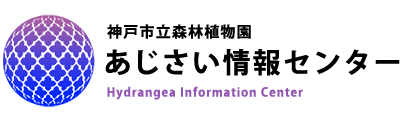あじさいにまつわる文化的情報・トピックス
花の色の変化
一般にあじさいの花の色は、植えられている土壌が酸性の場合は青色、アルカリ性の場合は赤紅色になる、といわれています。日本列島の土壌は酸性土壌のところが多いのですが、近年都市部を中心にコンクリート構造物が多くなり、その周辺ではアルカリ性の物質が溶け出し、赤紅色のあじさいもよく見かけるようになっています。
その仕組みはどうなっているのでしょうか。あじさいの花の色は、アントシアニンという植物界で広く存在する色素の状態に左右されます。土壌がアルカリ性のときは、アントシアニン本来の色である赤紫系の発色をしています。しかし、酸性に傾いてくると、土壌中のアルミニウムが溶けだしてイオン化しやすくなります。つまりアルミニウムイオン量が増えます。すると土壌中のアルミニウムイオンを含んだ水分が根を通してあじさいに摂取され、アントシアニン色素と結合し、青色を発色します。ということは、厳密に考えると、土壌中に元々アルミニウムが少なければ、また、その品種がアントシアニン色素をあまり持たない種であれば、あまり青くならない、ということになります。実際、関東・東海地方には白い花色の品種が多く見られますが、これらは基本的に色素をもたない品種なので、土壌が変わっても花色は変わりません。
他にも、日照や開花後の日数とか土壌中の水質や養分の質などによって、色素の結合状態はいろいろな状態に変わると考えられます。つまり、あじさいの花の色は、土壌が酸性・アルカリ性だというだけで変化するわけではないのです。
花色の変化もさることながら、自生のあじさいの花色は濁りがなく澄んだ発色をします。このような本来の清楚なあじさいを育てるには、肥料は控えめにして日照に注意することが大事です。

甘茶

みなさん、甘茶(アマチャ)ってご存知ですか? その名のとおり「甘い」「お茶」なのですが、これはヤマアジサイ系統種の中の一部の株の葉に甘味成分を含むものが発見され、その葉をお茶のように調製して飲用されるようになったのです。
古来より、4月8日の灌仏会(かんぶつえ)(お釈迦様の誕生日を祝う行事)ではお釈迦様の誕生仏に甘茶を注ぐという風習が行われてきました。当初は香を溶かしたお湯を用いていましたが、甘茶が広く飲用されるにつれ、代わりに甘茶が使用されるようになりました。
さて、甘茶はどうやって作るのでしょうか。葉を生のままでかじっても、よほど甘味成分を多く含んでいる葉でないかぎり甘さは感じません。地方によってその作り方はいろいろあるようですが、生葉を一度乾燥させ、水を噴霧してから発酵させたものを手で揉んで、さらに乾燥させて作るのが一般的なようです。この発酵は微生物によるものではなく、酵素によるもので紅茶やウーロン茶をつくる原理と同じです。
ここで甘味を感じさせている成分はフィロズルチンという物質で、砂糖の数百倍の甘さがあるといわれています。
日本では伊豆半島の天城地方に自生するアマギアマチャが非常に良質の甘茶になるので有名です。生産用としては、長野県・富山県・岩手県などでオオアマチャ・コアマチャが栽培されています。
フィロズルチンは他にも抗アレルギー作用があることが確認されています。
装飾花

あじさいといえば、真ん中に小さい花が集まって咲き、周りを囲むように美しいやや大きめの花びらを数枚持つ花が咲いているのを思い浮かべることと思います(これをガク咲きといいます)。真ん中の小さい花を「両性花」といって、オシベとメシベを持ち種子をつけます。これに対して周りの「花」は「装飾花(ほかにも不稔花・中性花ともいいます)」といい種子をつけない「飾り」の花です。分類学的には花びらではなく萼(ガク)が変化したものとされています。
装飾花は遠くからでもよく目立ち、虫などを誘き寄せるためのものだといわれています。
装飾花がボールのように密集した咲き方を手鞠(テマリ)咲きといいます。見た目はとても賑やかで美しいですが、両性花が少ないため種子が少ししかできません。
シチダンカ

六甲山であじさいといえばシチダンカを語らずにはいられません。ヤマアジサイの変種のひとつです。シーボルトの「日本植物誌」(1835年〜1870年にかけて刊行)に採録されていましたが、その後しばらくの間、実際に見かけられることがありませんでした。1959年(昭和34年)に荒木慶治氏によって六甲山地で「再」発見されました。装飾花が八重咲きとなり、各がく片が剣状に尖りきれいに重なって星状に見えるのが特徴です。現在では森林植物園内でも栽培しており、あじさい園でご覧いただくことができます。